一般外科・消化器外科
取り扱う主な疾患
消化器臓器(食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肛門、肝臓、胆嚢・胆管、膵臓)、脾臓、腹膜、腹壁に発生する外科的疾患が対象となります。 おおまかには腹部の諸臓器に食道を加えた領域の疾患です。
疾患としては、癌などの悪性腫瘍、良性腫瘍、潰瘍、胆石(胆嚢・胆管)、炎症性腸疾患、感染症、臓器の血行障害、腸閉塞、ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、その他)などがあり、そのほか、外傷、熱傷などの外科的治療を行います。
疾患としては、癌などの悪性腫瘍、良性腫瘍、潰瘍、胆石(胆嚢・胆管)、炎症性腸疾患、感染症、臓器の血行障害、腸閉塞、ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、その他)などがあり、そのほか、外傷、熱傷などの外科的治療を行います。
こんな時に受診してください~主な疾患と治療について
消化管疾患
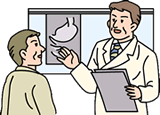
消化管は、食道-胃-十二指腸-小腸-大腸-肛門とひと続きの管で構成されています。消化管に問題のある場合、消化器症状として、「食事のつかえ」、「食後の吐き気や嘔吐」、「食欲がない」、「腹が張る」、「腹痛」、「便秘」、「下痢」、「便の異常(黒っぽい、赤っぽい、海苔や墨のよう)」、などの症状が見られます。便の色を気にすることは大切です。時々あるいは毎回黒っぽい便(泥状、軟便)がでる場合には消化管のどこかの出血性病巣(癌や潰瘍)が疑われます。これらの消化器症状が数日で改善しないか、しだいに増強する場合には早めの受診をお勧めします。排便時の赤色の出血はほとんどの場合「痔」が原因ですが、自己判断しないで診察を受けましょう。
消化管の癌が発見された場合、ごく早期のものは内視鏡的に切除することで完治が可能です。 しかし、早期癌でも内視鏡的に切除できない場合やすでに進行している場合は手術的切除が必要です。
胃の手術には部分切除、幽門側切除(胃出口側1/2~3/4の切除)、噴門側切除(胃入口側1/3~1/2の切除)、全摘出術などがあります。 幽門側切除、噴門側切除や全摘術では、術後に1回の食事量を少なくし回数を多くする工夫が必要となります。 胃切除後の摂取できる食事の量は術後数ヶ月から1年の間に少しずつ安定していくことが多く、最終的にどの程度の食事量がとれるかは個人差がありますが、術前と同じ位の食生活に回復される方も少なくありません。
大腸切除では、よほど広範囲の切除とならない限り大きな後遺症はありませんが、軟便、頻便などの便通異常をきたすことがあります。 大腸の中でも肛門に近い直腸という部位の手術では、肛門ごと切除して人工肛門を造らなければならないことがあります。直腸癌では病変が肛門に近いほど人工肛門を造る可能性が高まります。肛門を温存した直腸の切除では、便をためるという直腸の働きが低下するため、便秘や頻便など排便回数の異常が見られることが多くなります。
消化管の癌が発見された場合、ごく早期のものは内視鏡的に切除することで完治が可能です。 しかし、早期癌でも内視鏡的に切除できない場合やすでに進行している場合は手術的切除が必要です。
胃の手術には部分切除、幽門側切除(胃出口側1/2~3/4の切除)、噴門側切除(胃入口側1/3~1/2の切除)、全摘出術などがあります。 幽門側切除、噴門側切除や全摘術では、術後に1回の食事量を少なくし回数を多くする工夫が必要となります。 胃切除後の摂取できる食事の量は術後数ヶ月から1年の間に少しずつ安定していくことが多く、最終的にどの程度の食事量がとれるかは個人差がありますが、術前と同じ位の食生活に回復される方も少なくありません。
大腸切除では、よほど広範囲の切除とならない限り大きな後遺症はありませんが、軟便、頻便などの便通異常をきたすことがあります。 大腸の中でも肛門に近い直腸という部位の手術では、肛門ごと切除して人工肛門を造らなければならないことがあります。直腸癌では病変が肛門に近いほど人工肛門を造る可能性が高まります。肛門を温存した直腸の切除では、便をためるという直腸の働きが低下するため、便秘や頻便など排便回数の異常が見られることが多くなります。
胆石症
胆石症(胆嚢結石症)の 症状として典型的なのは、食後、特に脂っこい物を食べた数時間後、あるいは夜間に突然生じる強い右上腹部痛(肋骨弓の下の痛み)ですが、時には心窩部(みぞおち)、右背部、右わき腹の痛みが症状となることもあります。 胆石により突然生じる強い痛みを胆石発作といいますが、発作は繰り返すことが多く、また細菌感染により胆嚢炎をきたして重症化することがあります。
胆石症の治療は外科的治療が原則となります。これらの症状に思い当たる方は受診をお勧めします。当院では胆のう摘出術はほぼ全例腹腔鏡で行っています。 手術では胆石ごと胆嚢を摘出しますが、胆嚢を摘出しても暴飲暴食をしない限り、その後の食生活に影響を及ぼすことはほとんどありません。
何らかの検査で胆石が発見されても無症状な場合があり、これを「無症状胆石」といいますが、この場合は手術をせずに経過をみてもかまいません。 しかし、経過中に発作や胆嚢炎をきたす場合があります。症状がなくても、石が胆嚢に充満している場合(充満結石)や、胆嚢壁が石膏のように硬くなっている場合(石灰化胆嚢)、直径2cm以上の大きな胆石は、手術治療の対象となります。
胆石症の治療は外科的治療が原則となります。これらの症状に思い当たる方は受診をお勧めします。当院では胆のう摘出術はほぼ全例腹腔鏡で行っています。 手術では胆石ごと胆嚢を摘出しますが、胆嚢を摘出しても暴飲暴食をしない限り、その後の食生活に影響を及ぼすことはほとんどありません。
何らかの検査で胆石が発見されても無症状な場合があり、これを「無症状胆石」といいますが、この場合は手術をせずに経過をみてもかまいません。 しかし、経過中に発作や胆嚢炎をきたす場合があります。症状がなくても、石が胆嚢に充満している場合(充満結石)や、胆嚢壁が石膏のように硬くなっている場合(石灰化胆嚢)、直径2cm以上の大きな胆石は、手術治療の対象となります。
ヘルニア(脱腸)
足のつけ根の部分を鼠径部(そけいぶ)といいますが、この部分が立つと膨らみ、寝ると消失する場合、ソケイヘルニアと診断してまず間違いはありません。
成人以降、特に中年から高齢者に発生しやすく、加齢による筋肉や靱帯のゆるみが主な原因となります。 主なヘルニアとしては、男性に好発する鼠径ヘルニアと、女性に好発する大腿ヘルニアがあります。 乳幼児では男女を問わず先天的な原因で鼠径ヘルニアが発生します。
ヘルニアは体にもともとある筋肉や靱帯のすき間から、腸などのお腹の中の臓器が脱出するもので、手術による治療が必要です。 鼠径部がふくらむだけで痛みが無い場合は手術をせずに経過観察をしていても大丈夫です。 しかし、脱出した腸がお腹の中に戻れずに腸の腫れと血行障害を生じたり腸閉塞をおこすことがあります(嵌頓)。こうした場合には鼠径部の強い痛みや吐き気・嘔吐をきたし、緊急手術が必要となる場合もありますので、すぐに受診してください。
以前はヘルニアの原因となる筋肉や靱帯のすき間(ヘルニア門)を、縫合により閉鎖していました。しかし、この方法では補強に利用したもともとの筋肉や靱帯が弱くなって再発の原因になったり、手術部の突っ張る痛みが長く続くことがあります。 このため、最近では人体に害のない人工膜(メッシュ)で筋肉の補強とヘルニア門の閉鎖を行う方法が普及しており、再発率の低下と術後の痛みの軽減に効果があります。 当科でも中年以降の患者さんには原則としてこの人工膜を利用した手術を行っています。 最近はヘルニア手術においても腹腔鏡手術が主流となり、さらに術後疼痛は軽減されています。
成人以降、特に中年から高齢者に発生しやすく、加齢による筋肉や靱帯のゆるみが主な原因となります。 主なヘルニアとしては、男性に好発する鼠径ヘルニアと、女性に好発する大腿ヘルニアがあります。 乳幼児では男女を問わず先天的な原因で鼠径ヘルニアが発生します。
ヘルニアは体にもともとある筋肉や靱帯のすき間から、腸などのお腹の中の臓器が脱出するもので、手術による治療が必要です。 鼠径部がふくらむだけで痛みが無い場合は手術をせずに経過観察をしていても大丈夫です。 しかし、脱出した腸がお腹の中に戻れずに腸の腫れと血行障害を生じたり腸閉塞をおこすことがあります(嵌頓)。こうした場合には鼠径部の強い痛みや吐き気・嘔吐をきたし、緊急手術が必要となる場合もありますので、すぐに受診してください。
以前はヘルニアの原因となる筋肉や靱帯のすき間(ヘルニア門)を、縫合により閉鎖していました。しかし、この方法では補強に利用したもともとの筋肉や靱帯が弱くなって再発の原因になったり、手術部の突っ張る痛みが長く続くことがあります。 このため、最近では人体に害のない人工膜(メッシュ)で筋肉の補強とヘルニア門の閉鎖を行う方法が普及しており、再発率の低下と術後の痛みの軽減に効果があります。 当科でも中年以降の患者さんには原則としてこの人工膜を利用した手術を行っています。 最近はヘルニア手術においても腹腔鏡手術が主流となり、さらに術後疼痛は軽減されています。
手術前の検査について
手術を行う前に必要な検査には大きく分けて2種類あり、1つは病気の診断のための検査で、もう1つは手術の安全性・危険性を評価するための検査です。
1. 診断のための検査
X線検査、造影検査、内視鏡検査、超音波検査、CT検査、MRI検査などがあり、肝臓や脾臓の手術などでは血管造影検査も行われます。これらの検査を円滑に、またなるべく迅速に進めるために入院していただくことがあります。(消化器内科・放射線科で施行することがほとんどです)
2. 手術の安全性・危険性を評価するための検査
全身の状態や合併疾患の症状を評価し、手術する上でどのような準備や注意が必要か、あるいは手術がどの程度安全に行えるかなどを評価するための検査です。血液・尿検査、心電図、肺機能検査などを中心に、重要な臓器である、心、肺、肝、腎などの機能をチェックします。
手術、入院中の治療について
手術前には、外科医・内科医・放射線科医を交えて、患者さんの病気を診断し、それに対する最も望ましい治療法を検討し、外科入院後は主治医が中心となって患者さんの治療を担当します。 週に1回は外科医全員で入院患者さん全員の病状や治療方針を検討する会を設け、外科チームとして共通の理解と方針のもとに患者さんの治療を進めていけるようにしています。
基本的には各学会から出されているガイドラインに沿った治療方針になりますが、患者様の年齢・体力・基礎疾患・社会的状況など十分考慮・相談し、治療法を決定していきます。
外科入院後は、手術前に主治医が患者さんや家族の方へ病状や手術内容の詳しい説明を行い、術後は手術の結果や今後の治療についての説明をいたします。 家族の方がさらなる説明を希望される場合、主治医あるいは病棟の看護師に伝えていただければ日時を調整して説明いたします。
開腹手術は全身麻酔で行われますので、麻酔がかかった後は手術が終了して麻酔が覚めるまで意識はなく、痛みを感じることはありません。 手術後は傷の痛みが数日続きますので、硬膜外麻酔あるいは鎮痛薬の静脈内持続注入により痛みを和らげるようにしています。 多くの患者さんは手術翌日から歩行などの離床を開始でき、術後1週間の内に歩行・トイレ・洗面などが十分に可能な状態となります。
胃や腸を切除する消化管の手術では術直後は絶飲食となり、点滴で栄養と水分の補給を行います。 食事の開始時期は術後3日目以降となることが多いですが、飲水は食事開始の1~2日前から可能となります。 食事は流動食から始まり1~2日ごとに3部粥、5分粥、7分粥、全粥、米飯と進み、術後1から2週間ほどで退院となります。 胃や腸を切除をしない手術(肝臓切除術、胆嚢摘出術、その他)では飲水・食事はより早く始まります。
現在、胃切除術、大腸切除術、胆嚢摘出術、鼠径ヘルニア手術については、病状・手術内容・術後経過などをわかりやすく解説した手術説明書と入院治療計画書をお渡ししていますので、 病気や治療に対する理解を深めていただけると思います。
基本的には各学会から出されているガイドラインに沿った治療方針になりますが、患者様の年齢・体力・基礎疾患・社会的状況など十分考慮・相談し、治療法を決定していきます。
外科入院後は、手術前に主治医が患者さんや家族の方へ病状や手術内容の詳しい説明を行い、術後は手術の結果や今後の治療についての説明をいたします。 家族の方がさらなる説明を希望される場合、主治医あるいは病棟の看護師に伝えていただければ日時を調整して説明いたします。
開腹手術は全身麻酔で行われますので、麻酔がかかった後は手術が終了して麻酔が覚めるまで意識はなく、痛みを感じることはありません。 手術後は傷の痛みが数日続きますので、硬膜外麻酔あるいは鎮痛薬の静脈内持続注入により痛みを和らげるようにしています。 多くの患者さんは手術翌日から歩行などの離床を開始でき、術後1週間の内に歩行・トイレ・洗面などが十分に可能な状態となります。
胃や腸を切除する消化管の手術では術直後は絶飲食となり、点滴で栄養と水分の補給を行います。 食事の開始時期は術後3日目以降となることが多いですが、飲水は食事開始の1~2日前から可能となります。 食事は流動食から始まり1~2日ごとに3部粥、5分粥、7分粥、全粥、米飯と進み、術後1から2週間ほどで退院となります。 胃や腸を切除をしない手術(肝臓切除術、胆嚢摘出術、その他)では飲水・食事はより早く始まります。
現在、胃切除術、大腸切除術、胆嚢摘出術、鼠径ヘルニア手術については、病状・手術内容・術後経過などをわかりやすく解説した手術説明書と入院治療計画書をお渡ししていますので、 病気や治療に対する理解を深めていただけると思います。
癌を心配される方へ
今や3人に1人は癌で亡くなるといわれています。しかし、早期癌であれば内視鏡や腹腔鏡など体の負担が少ない治療法ができますし、治る可能性も高くなります。一方で、癌はある程度進行しなければ症状が現れません。 消化管の癌(食道癌、胃癌、大腸癌)が早期で発見されるのは、健診で異常を指摘されたり、別の病気でたまたまX線造影や内視鏡検査を受けたりして見つかる方がほとんどです。中年(40歳~)以降は癌の発生しやすい年齢です。症状が出てからでは進行癌となっている可能性が高いので、定期的な健康診断を受けるように心がけてください。
食道、胃、大腸の癌は造影検査や内視鏡検査で発見されやすい癌で、ごく早期に発見されれば手術をしないで内視鏡的に切除できる場合があります。 内視鏡的に切除できない癌や進行した癌は手術で切除するのが最も良い治療法です。早期であれば治る可能性は大変高く、たとえ外科手術となっても傷の小さな腹腔鏡下手術が可能となります。進行癌でも手術と抗癌剤治療で治る可能性が高くなってきました。当院では「癌の病名を告知する」ことを原則としています。もし癌と診断されても、必要以上に心配されることなく医師から十分な説明を受けて前向きに治療を考えてください。
食道、胃、大腸の癌は造影検査や内視鏡検査で発見されやすい癌で、ごく早期に発見されれば手術をしないで内視鏡的に切除できる場合があります。 内視鏡的に切除できない癌や進行した癌は手術で切除するのが最も良い治療法です。早期であれば治る可能性は大変高く、たとえ外科手術となっても傷の小さな腹腔鏡下手術が可能となります。進行癌でも手術と抗癌剤治療で治る可能性が高くなってきました。当院では「癌の病名を告知する」ことを原則としています。もし癌と診断されても、必要以上に心配されることなく医師から十分な説明を受けて前向きに治療を考えてください。
腹腔鏡下手術について
腹腔鏡とは、お腹の中を観察するための直径3mm~1cm程の筒状の内視鏡です。この腹腔鏡を使ってする手術を腹腔鏡下手術といい、全身麻酔で行われます。 実際には、お腹に1cm前後の小さな傷を何カ所かつけて、お腹に穴を開け、1つの穴には腹腔鏡を挿入してお腹の中をテレビモニターに映して観察し、別の穴から、鉗子という細いマジックハンドの様な器具を使って手術をするものです。日本では1990年頃より日本で行われるようになり、胆嚢結石に対する胆嚢摘出術から始まりました。その後、手術器具や術式が進歩し、今では食道癌・胃癌・大腸癌などの悪性疾患に対しても行われています。お腹を大きく切開しないことで、手術後の痛みが少ない・術後の回復が早い・傷跡が小さく美容的に優れる、などという利点があります。さらに、傷が小さいので術後の癒着が少なくなり術後腸閉塞の可能性が減少すると考えられています。また、拡大視効果と言って臓器や血管などを非常に拡大して見ながら手術するので、開腹手術に比べて精密な手術か可能です。実際、臓器によっては術後成績や合併症発生率などで開腹手術と遜色ないというデータが出ています。こうした理由から、当科では積極的に腹腔鏡下手術を行っています。
しかし、同じ病名でも癌の進行度や全身状態などによって腹腔鏡下手術の適応とならない場合があります。また、途中何らかの理由で腹腔鏡下手術が続行困難な状況になることがあり、この場合は開腹手術に切り替えて手術を完遂します。
しかし、同じ病名でも癌の進行度や全身状態などによって腹腔鏡下手術の適応とならない場合があります。また、途中何らかの理由で腹腔鏡下手術が続行困難な状況になることがあり、この場合は開腹手術に切り替えて手術を完遂します。
当科で施行している鏡視下手術
胃癌・異腫瘍に対する腹腔鏡下胃部分切除・幽門側胃切除・噴門側胃切除・胃全摘術
胃・十二指腸腫瘍穿孔に対する腹腔鏡下穿孔部縫合閉鎖術
結腸・直腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除術
肝嚢胞に対する腹腔鏡下肝嚢胞開窓術
肝腫瘍に対する腹腔鏡下肝部分切除・外側区域切除術
胆嚢疾患に対する腹腔鏡胆のう摘出術
脾臓疾患に対する腹腔鏡下脾摘出術
脾疾患に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術
腸閉塞症に対する腹腔鏡下腸管癒着剥離術
鼠径部ヘルニア・臍ヘルニア・腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術
虫垂炎に対する腹腔鏡下中垂切除術
診断的腹腔鏡検査 など
豊川市および周辺地域の住民の方々の健康と生活を守ることが我々の使命と考えています。気になる症状がある方や健康診断等で異常を指摘された方は、是非早めに当院を受診してください。
胃・十二指腸腫瘍穿孔に対する腹腔鏡下穿孔部縫合閉鎖術
結腸・直腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除術
肝嚢胞に対する腹腔鏡下肝嚢胞開窓術
肝腫瘍に対する腹腔鏡下肝部分切除・外側区域切除術
胆嚢疾患に対する腹腔鏡胆のう摘出術
脾臓疾患に対する腹腔鏡下脾摘出術
脾疾患に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術
腸閉塞症に対する腹腔鏡下腸管癒着剥離術
鼠径部ヘルニア・臍ヘルニア・腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術
虫垂炎に対する腹腔鏡下中垂切除術
診断的腹腔鏡検査 など
豊川市および周辺地域の住民の方々の健康と生活を守ることが我々の使命と考えています。気になる症状がある方や健康診断等で異常を指摘された方は、是非早めに当院を受診してください。
担当医師の紹介
| 医師名 (専門分野) |
出身大学 (医局) |
役職名 | 資格 |
| 寺西 太 | 名市大 | 副院長 診療局長 外科部長 消化器外科部長 |
日本外科学会外科専門医 日本外科学会認定医 日本消化器外科学会消化器外科指導医・専門医 インフェクションコントロールドクター(ICD) 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 臨床研修指導医 |
| 堅田 武保 | 名市大 | 外科主任部長 消化器外科主任部長 |
日本外科学会指導医 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会指導医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 身体障碍者手帳指定医 麻酔科標榜医 臨床研修指導医 |
| 小出 修司 | 名市大 | 消化器外科部長 | 日本外科学会外科専門医 |
| 仲井 希 | 名市大 | 消化器外科部長 外科部長 |
日本外科学会外科専門医 日本消化器外科学会指導医・専門医 日本内視鏡外科学会技術認定医(大腸) 日本内視鏡外科学会 評議員 日本ロボット外科学会専門医(国内B級) 日本内視鏡外科学会ロボット支援手術プロクター(直腸・結腸) 臨床研修指導医 |
| 西土 徹 | 名市大 | 外科医長 | 日本外科学会専門医 麻酔科標榜医 |
| 柳田 剛 | 外科医長 消化器外科医長 |
||
| 山本 真也 | 名市大 | 医員 | |
| 山崎 礼雄 | 医員 | ||
| 鈴木 海太 | 医員 |
手術件数
※( )内は腹腔鏡下手術件数
| 腹部 | 疾患名 | 2022年 |
| 胃 | 胃癌 | 27(24)件 |
| 胃GIST | 3(3)件 | |
| 胃・十二指腸潰瘍 | 11(11)件 | |
| 胃・十二指腸その他 | 4件 | |
| 小腸 | 小腸GIST | 1(1)件 |
| 腸閉塞 | 29(29)件 | |
| その他 | 3件 | |
| 下部消化管 | 結腸癌 | 80(腹腔鏡:72、ロボット:1)件 |
| 直腸癌 | 48(腹腔鏡:30、ロボット:17)件 | |
| 大腸その他 | 53件 | |
| 虫垂炎 | 53(53)件 | |
| 痔核・痔瘻 | 7件 | |
| 肝胆膵 | 原発性肝腫瘍 | 4(1)件 |
| 転移性肝腫瘍 | 4(3)件 | |
| 胆石症 | 106(106)件 | |
| 胆のうポリープ | 1(1)件 | |
| 膵頭部癌 | 2件 | |
| 膵体尾部癌 | 2(1)件 | |
| 膵その他 | 1(1)件 | |
| 体表 | 鼠径部ヘルニア | 100(84)件 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 6件 | |
| 体表その他 | 8件 |





